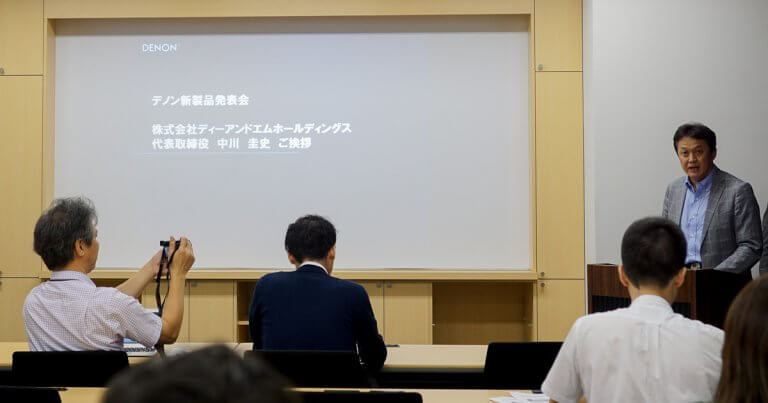600NEシリーズとPolk Audioのスピーカーで6枚のアルバムを聴いてみた

スマホとヘッドホンで音楽を聴くのも気軽で便利ですが、たまにはHi-Fiシステムでじっくりと音楽を聴いてみませんか。今回はデノンHi-Fiシステムのエントリーモデル600NEシリーズを3種類のPolk Audioのスピーカーで音楽・映画・旅行ライター前原利行さんにお気に入りの音源で試聴してもらいました。
600NEシリーズとPolk Audioのスピーカーを組み合わせて、ロックからジャズまで6枚のアルバムを聴いてみた
フリーのライター(兼編集)という仕事をしているので、たまの取材を除けば、仕事時間の多くは在宅仕事。そんな自分の生活に欠かせないのが音楽です。今はサブスクやPCに取り込んだ状態で音楽を聴くことが増えてしまいましたが、数年前まではCDプレーヤーで音楽を聴いていました。だからCDは1000枚近くあり、それが食器棚まで侵食しているほどです。
今回、デノンオフィシャルブログ編集部から、CDプレーヤー、アンプ、スピーカー一式を自宅の環境で試してみませんかというお誘いを受けました。「久しぶりにガッツリと音楽が聴けるぞ」とうれしく思うと同時に、「いったいどこに置くべきか?」という、うれしい問題も持ち上がりました。テレビを置いている寝室も考えましたが、正直、私が家でほとんどいるのは仕事部屋なので、そちらのテーブルに設置することにしました。

セットアップはつなぐだけなので説明書もいらないほど簡単。設置した瞬間から、部屋の中心はこのステレオシステムになりましたね。今回お借りしたスピーカーは3種類ありますが、一度に机の上に全部は置けないので、一つずつ箱から取り出し、残りを机の下に収納しました。





600NEシリーズのCDプレーヤーとアンプの組み合わせ
CDプレーヤーのDCD-600NEは、基本は再生するだけのごくごくシンプルなもの。フロントにはヘッドフォンジャックの端子もありません。アンプのPMA-600NEのつまみもシンプルです。「ANALOG MODE」というのがありますが、これはデジタル入力回路への電源供給をストップしてノイズを減らすものなので、CDを聴くときは「ANALOG MODE」をオンにしっ放しです。隣の「SOURCE DIRECT」のボタンは、その下にある音質調節回路のBASS、TREBLE、BALANCEを通らないため、より原音に忠実な再生ができると説明書にあります。ですので、ここもON。良い音のため、できるだけ余計な回路を通らないという設計なのですね。

音楽を再生してみたところ、まず部屋で適当な音量で聴く場合、ボリュームのつまみが9時の位置まで上がるということがないということに驚きました。昼でも8時か8時半の位置。夜なら7時半の位置で十分。いったいどこまで出力できるのでしょう。なので、最初はうっかり大音量で鳴らさないように気をつけました。それに小さな音でも、中低音がバランスよく聴こえるので、問題ありません。
家にあるCD約1000枚はほとんどがロック、ポップスで、200枚ぐらいがジャズ、100枚ぐらいが映画音楽やクラシックです。600NEシリーズでそれらをまんべんなく聴いてみた感想は「中低音がとても豊かに聴こえる」ということでした。持っているCDはバンド編成の曲がほとんどなのですが、注目したのはベースの音です。小さなスピーカーや小さな音量で聴くと、ベースの音がペケペケと高音しか聴こえなくなることがあるのですが、その点、このデノンのDCD-600NEとPMA-600NEの組み合わせだと、小さな音量でもベースがはっきり、しかもふくよかに聴こえます。そして音量を上げていくと、奥行きというか、さらに空間も感じられていきます。その分、ハイをガンガン聴きたいという人には刺激が足りないかもしれません。総じて大人の耳に心地良い、ずっと聴いていても疲れない品の良いサウンドがこの組み合わせの持ち味と思いました。
さて、ここからはスピーカーごとに楽しめたCDを2枚ずつ紹介しましょう。
Signature Eliteシリーズ ES20との組み合わせ

最初に試したスピーカーということもあり、以下これが基準になってしまいました。第一印象で中低域の再生がよく感じたので、まずは古い録音ものから試してみるとことにしました。
アーティスト名:ローリング・ストーンズ
アルバム・タイトル:『12×5』(1964)2002リマスター盤
ビートルズに比べ、60年代のローリング・ストーンズの録音はずっと悪いと思っていました。音の分離が悪く、特にビル・ワイマンのベースは遠くでモコモコ鳴っていてよくわからないという印象です。そこで取り出したのがローリング・ストーンズの米盤セカンドアルバムです。
このシステムで聴くと、まずワイマンのベースラインがはっきり聴こえ、さらに奥行きも立体感もあります。きちんと録音されていたのだなあと再評価。ブルースのカバーバンドとしてのストーンズは、この頃が最高なのだろうなあと感じました。同じジャケット写真の英国盤は、選曲も異なり、モノラルなのでご注意ください。
Around and Around – The Rolling Stones
アーティスト名:ホール&オーツ
アルバム・タイトル:『ザ・ベスト・オブ・ダリル・ホール&ジョン・オーツ』
ビル・ワイマンのベースが発見だったので、そこからベースの音が小さかった印象がある80年代MTVミュージックを聴いてみようと思いついたのが、ホール&オーツの大ヒット曲「プライベート・アイズ」(1981)。これはその曲が入っているベスト盤です。おお、まるで印象になかったベースの音が存在感を増していい感じ。同じアルバムに入っていた「アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット」は、逆にもとからベースメインの曲でしたが、ここではベースがうるさくならずにサウンドに調和して小気味よい感じになっています。「セイ・イズント・イット・ソー」(1984)といった80年代半ばのサウンドも、軽薄ではなく、豊かな大人の音楽として聴けました。
I Can’t Go For That (No Can Do) – Daryl Hall John Oates
Reserveシリーズ R200

こちらはES20よりも上位シリーズで、深みのある低音があり、中音から高音にかけても豊か。包み込むような音場を感じました。なので、楽器でいうとエレピを聴きたいと思いました。
アーティスト名:マイルス・デイビス
アルバム・タイトル:イン・ア・サイレント・ウェイ
もう名盤中の名盤ですね。マイルスの正規盤はほとんど持っています。A面を占める「シュー/ピースフル」がとにかく最高です。左にジョン・マクラフリンのギター、右にハイハットをひたすら刻み続けるトニー・ウィリアムズのドラム、そして中央に全体を包み込むチック・コリアとハービー・ハンコックのエレピ(渾然一体としていてどちらが弾いているのかわかりません)と曲を支配するドローン効果のあるデイブ・ホランドのベース。もちろんのその上でトランペットを吹く、マイルスの音数の少ない簡潔なメロディーがすばらしい。このセットでそのサウンドに没入。どっぷりと聴き込んでしまいました。
Shhh / Peaceful – Miles Davis
アーティスト名:ジェフ・ベック
アルバム・タイトル:ブロウ・バイ・ブロウ
みなさんの家にも1枚はあるのでは?というジェフ・ベックの大名盤。2曲目の「シーズ・ア・ウーマン」では特に左右のエレピが立体的にグッと出てきて、そのリズムの気持ちの良さに浸っているうちに、肝心のベックのギターを聴くのを忘れてしまいそうになります。このアルバムは、とにかくマックス・ミドルトンのエレピが格好いい。中低域がまろやかに混ざって広がって聴こえます。クレジットはないのですが、7曲目の「セロニアス」ではスティービー・ワンダーがファンキーなクラヴィネットを弾いています。プロデューサーはジョージ・マーティン。
Monitor XTシリーズ MXT20

3台のスピーカーの中ではサイズは最も小さく、低価格帯のものです。そのためか、他の2つに比べると高音やアタック音がくっきりと出る気がしたので、アメリカン・ロックをチョイスしました。パーカッシブなギターのアタック音やドラムの乾いたスネアなどが聴いていて気持ちいい感じですね。
アーティスト名:ボブ・ディラン
アルバム・タイトル:オー・マーシー
ボブ・ディランは自分のフェイバリット・ミュージシャンで全アルバムを持っています。その中からこのスピーカーで試したくなったのは、1989年のニューオーリンズ録音のこのアルバムです。1曲目、ドラムとパーカッションが渾然一体となって奏でる「ポリティカル・ワールド」をMXT20で聴くと、アタック音の迫力が増して、音の洪水の中でディランが歌っているように聞こえてくる。その分、ボーカルは沈みがちかもしれませんが、それが新鮮で格好良いのです。スローな曲ではディランの声の存在感が増し、あらためて歌の上手い人だということがわかります。アルバムによってサウンドの出来不出来があるディランですが、このアルバムはU2のボノの紹介で起用されたプロデューサーのダニエル・ラノワがディランの良さをうまく引き出しています。ただしディランの自伝を読むと、ディラン自身は録音には相当煮詰まったようです。
Political World – Bob Dylan
アーティスト名:トム・ペティ
アルバム・タイトル:ワイルド・フラワーズ
アメリカ、それもウエストコースト系の乾いたサウンドが合いそうと聴いた中で、ボズ・スキャッグス『ダウン・トゥー・ゼン・レフト』、フリートウッド・マック『ファンタスティック・マック』も良かったのですがもう少し後の時代の、日本ではあまり有名ではありませんが、アメリカではロックの名盤と言われているこのアルバムをあげてみました。トム・ペティはバンドのトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズと並行してソロ活動もしており、3枚のソロ作品を出しています。これは1994年に発売された2枚目のソロアルバムで、リック・ルービンがプロデュース。アメリカン・ロックの王道で、楽曲が良いものが揃っており、各楽器のバランスや、ドラムのスティーブ・フェローンのリズムが心地よく伝わってきます。
You Don’t Know How It Feels – Tom Petty
ということで各CDの音楽性はバラバラですが、聴き馴染んだ自分の愛聴盤でサウンドチェックしてみました。手頃な価格なので、自分用にも欲しいと密かに思っています。

 前原利行(まえはら・としゆき)
前原利行(まえはら・としゆき)
音楽・映画・旅行ライター。映画や音楽、アート、歴史など海外カルチャー全般に興味を持ち、執筆している。世界史オタク。この2年で国内旅行も記事を書くほど詳しくなった。早く海外の音楽フェスにも復帰したいところ。
Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事
HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編
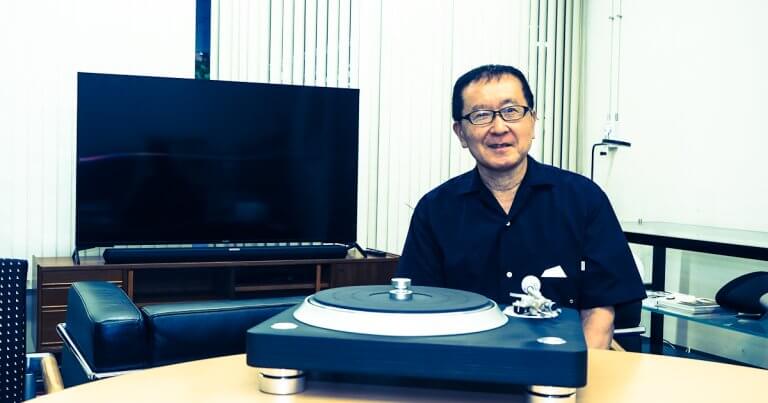
レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 前編

山内セレクション@2023東京インターナショナルオーディオショウ featuring DP-3000NE レ…