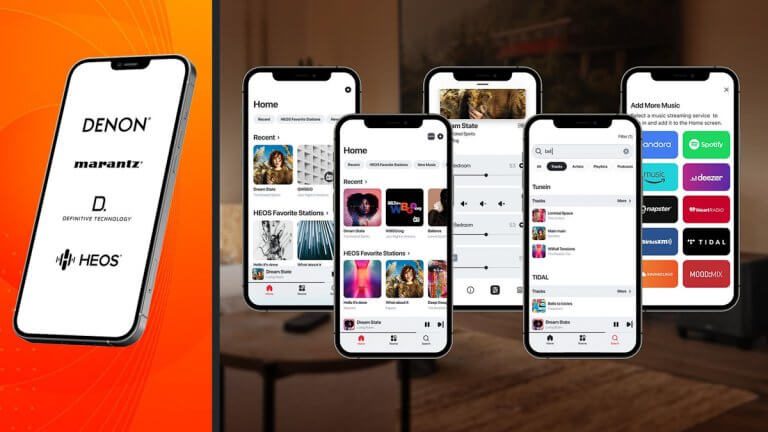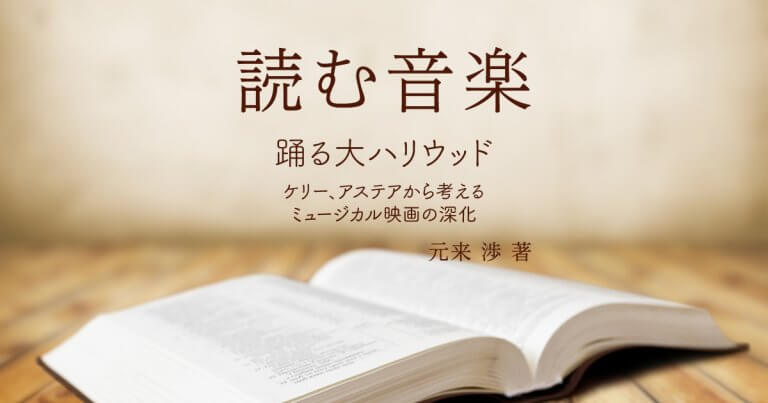デノンの品質保証 Vol.2

D&M白河工場はデノン製品の設計、生産だけの拠点であるだけでなく、品質保証の拠点でもあります。QA(品質保証)部門インタビューVol.2は製品が落とされたり埃まみれにされたりする検査試験棟を見学します。
QAとはQuality Assurance、つまり品質保証のこと。デノンのハイエンドモデルが生産されているD&M白河工場は、設計、生産の拠点であるだけでなく、自社の検査施設を持つ品質保証の拠点でもあります。
品質保証という観点から見たデノンの哲学とは?
QA(品質保証)部門インタビューVol.2は製品が落とされたり埃まみれにされたりする、過酷な検査試験棟を見学します。

↑福島県白河市にあるD&M白河工場

【今回のナビゲーター】
今回のナビゲーターは品質保証部QAグループの二宮 賢寿と橋本 大輔です。
二宮 賢寿(右)
橋本 大輔(左)
前回からの続き
前回のブログはこちらからご覧ください
■前回デノンの品質保証についての考え方をうかがいました。今回はいよいよ別棟にある検査試験棟の見学をお願いします。
二宮:わかりました。ご案内します。

↑試験検査棟入り口
二宮:ここが試験検査棟です。この試験検査棟には全部で7種類の検査試験用の設備があります。
1. 落下試験、2. 振動試験、3. エージング試験、4. 塵埃試験、5. スタック試験、6. 環境試験、7. 雷サージ試験、の7つです。
まず落下試験からご案内しましょう。
■おお、荷物を落下させるための専用の試験機械があるんですね。

二宮:はい。これが落下試験機です。ここでは梱包された状態で製品の落下強度を試験しています。
落下試験はJISの規格に則っており、箱の角と縦稜が30cm、底面稜が60cm、そして箱の底面が70cm、その他5面が60cmの高さからの落下テストを行っています。
またJIS規格より厳しいものですが、デノンの独自の検査規格として100cmから落下させる限界テストも行っています。
橋本:ちょっと落としてみましょうか。

橋本:こんな感じで箱を支えているアームが引っ込んで落下する仕組みになっています。
下は平面で硬いコンクリートとなっています。
●落下試験では、たとえばどんな壊れ方をするのですか。
二宮:最近は限界テストでもまず製品が壊れませんが、以前は重いAVアンプなどの場合、内部の基板が破損するといったことがありました。
橋本:落下試験に関連したものとして、振動試験があります。こちらは梱包状態でトラック、鉄道、航空機の輸送を想定した試験となっています。

二宮:これが振動試験用の機械です。トラックの荷台のように振動するように作られていて、振動は垂直方向である上下運動と、水平方向である左右の両方向で振動させることができます。ここでも規格に則って振動させ、耐久性を検査します。こちらも動かしてみましょうか。
■おー、結構激しく揺れています。トラックでの荷台ってけっこう揺れるものなんですね。
ここでは製品にどんな不具合が起きるのでしょうか。
二宮:振動のような一発の衝撃ではなく、製品に長時間mp振動が加わりますから、基板を留めているネジが緩んだりすることがあります。
また梱包材、緩衝材などの包装の性能のチェックでもあります。
■ありがとうございました。では次をお願いします。
二宮:次はエージング試験ですが、エージング試験に関しては生産工場の中に出荷前にエージングを行う設備があるので、そこで行っています。
※製造工程でのエージング(ヒートラン)については前回のブログをご覧ください。
■新製品の認定時のヒートランは実際に製造している製品のヒートランとはどう違うのでしょうか。

橋本:実際に製造している製品のヒートランは不具合をチェックするだけでなく、クルマで言うとパーツを馴染ませる慣らし運転の意味も含まれています。
我々の新製品の認定でのエージング、つまり稼動試験は実際の使用環境や使用方法で稼動させて仕様通りに性能が出ているか、不良箇所がないかをチェックします。
ですから製造のヒートランは気温35度の環境で24時間程度の連続運転を行いますが、QAの認定試験では量産手前のパイロットランを35度で20台、100時間連続で動かします。
CDプレーヤーのドライブなど、新規メカを搭載したモデルに関しては100台を100時間回します。
つまり100台で100時間ぶっ通しでCDを再生するわけです。それで1台も問題が発生しないかを検証します。
■相当厳しいですね。35度かなり暑いですが、もっと暑かったり寒かったりの試験があるんですよね。
二宮:はい。それがこちらの環境試験用の機械です。
設定した温度と湿度を保つことができるので恒温恒湿槽といいます。
この検査試験棟には恒温恒湿槽が6台あります。

↑恒温恒湿槽
二宮:たとえばこちらの恒温恒湿槽ではスタック試験をしています。

↑スタック試験
橋本:今このプリメインアンプは気温40度で湿度が90%の状態で上に250キロのウェイトを載せています。
■過酷ですね。これは何を試験しているのですか。
二宮:これはコンテナの中に製品が積まれて置かれていることを想定した試験です。
コンテナは40度、90%という過酷な状況にもなりますし、積み上げられた場合大きな荷重がかかります。
そこで「コンテナの高さいっぱいに箱を積むと何段詰めるか」を計算し、その段済み数に1段分マージンをかけて荷重を算出し、その重量を梱包された製品にかけています。
試験が終わったあと、本体の機能や性能も当然チェックしますが、段ボールや緩衝材が湿気で弱ったり取り出す際に緩衝材が本体に付着しないか、といった点も見ています。

橋本:それとは別に、倉庫でストックされている状態を再現する保存試験もありまして、こちらは梱包状態で気温60度/湿度90%、またはマイナス20度。そういった状況に3日間置いておきます。
これも試験後に性能を見ますが、これは船便などを意識した試験です。
寒い国もあれば暑い国もありますので、こうしたシミュレーションも行います。
二宮:これらは梱包状態での検査ですが、環境検査では実際に動作させて検査を行います。
デノン製品は仕様として気温は5度から30度、湿度は60%までの動作を保証しています。
我々はそこにさらにマージンをとり、低温は0度、高温は40度、湿度90%の状態で動作させて動作確認と性能測定を行います。
そして低温に関してはマイナス10度でも動作確認を行っています。
■マイナス10度で動作確認ですか。そうとう寒いですよね。
二宮:寒いです(笑)。

■中を見せてください。あ、やはりすごいことになってますね。本体に霜が降りています。
二宮:この状態で電源を投入してCDプレーヤーであればCDが再生できるか、AVRであれば音と画像がしっかり処理できて出力できるかを確認します。
ただし機種によっては使用しているパーツがマイナス10度までの動作を保証していない場合がありますので、モデルによっては低温の設定は変わります。

■マイナス10度で音楽を聴く人はいるのでしょうか。
二宮:それは恐らくいないとは思います。
このマイナス10度での動作試験も以前はなかったのですが、あるとき「低温で電源を入れたらノイズが出た」というクレームがありました。
それで0度などで再現性をみたのですが、部品でバラツキが出る。
完全に再現性が得られたのがマイナス10度でした。
それでこの試験が追加になりました。かなり前の話ですが。
■マイナス10度で中に入るのはキツいですね。
二宮:このような操作用の小さな窓がありますので、そこから手だけを入れて操作を行います。

二宮:ちなみにデノンで以前カーステレオを手がけていましたが、その時は80度とマイナス20度でも試験していました。
もっときつかったです(笑)。
■さて別室に来ましたが、ここにも似た恒温恒湿槽のような部屋がありますね。

二宮:ここは低温試験といって気温10度、湿度10%に設定されています。
橋本:冬場に乾燥していると静電気が起きやすいじゃないですか。
ここではそういう帯電しやすい状況をわざと作り出して、CDなどを再生したときにノイズが出ないかを確認しています。
以前は製品としてカセットプレーヤーもありました。
カセットプレーヤーだと帯電してテープにノイズを録音してしまうこともありましたので、そういったチェックもしていました。

■こちらは相当ものものしい試験装置ですね。塵埃試験とはどんな試験ですか。

二宮:塵埃試験とは、ホコリやチリ、タバコの煙など様々な大きさのホコリがある中で正常に可動できるかを試験します。
主にCDプレーヤーなどの回転機器搭載で、製品のボトムに風穴が空いているモデルを対象に試験を行います。
■窓にワイパーがついているぐらいホコリまみれの状態ですね。この状況で稼動させるのでしょうか。

↑塵埃試験装置の内部。手前と後ろの窓にはホコリを払うワイパーが装備されている。
二宮:そうです。
■このホコリはなんですか。
二宮:これもJISの規格に準拠した試験で、粉塵も実験用の粉体で関東ローム層の微粒子です。
これも試験の規格がありますのでそれに沿った時間、沿った量で噴射し、6時間連続で再生します。

↑粉体を実験室に吹き込む装置
■これもかなり過酷ですね。
二宮:この試験も以前業務用の機器をデノンで製造していた時期があって、その頃のクレームがきっかけとなって開始されたものです。カラオケでCDを再生する業務機を作っていたのですが、カラオケボックスの中でCDが読み取れなくなる、それで検査したところ、タバコのヤニがCDのピックアップに付着して読み出しができなくなることが分かりました。
■タバコのヤニで?
橋本:カラオケボックスの中は狭いですし、当時はタバコの煙もモクモクでしたから。
それでCDが読めなくなりました。
■ちなみに塵埃試験のような大がかりな試験装置は、他社の工場にもあるのが普通ですか?
二宮:他社のことはわからないのですが、あまり自社で塵埃試験の検査はやっていないと思います。
■次は前回のインタビューの冒頭にお話が出た「雷サージ試験」ですね。
二宮:はい。こちら雷などで瞬間的に発生する大電流(サージ電流)が起きた際、製品に不具合が起きないか確認する試験です。
IEC規格による雷サージ試験は1キロボルトですが、我々はマージンをとり、その倍の2キロボルトで検証試験をしています。

↑雷サージ試験
■これも自社で実験施設を持っている工場は少ないのではないでしょうか。
二宮:確かにそうかもしれません。もし自社でこうした検査できないのであれば、検査ができる機関に委託しなくてはなりません。
それは時間がかかりますし、不具合が出た時にすぐにまた検査をしてもらえるとは限りません。
その点、検査装置を自社で持っていれば問題があった時にフィードバックがすぐでき、何度でも検証してすぐに対策できます。
■これで試験装置は全部見せていただきました。ありがとうございました。
D&M白河工場は設計、製造そして検査施設を自前で揃えている品質保証グループもあります。
これの部署が同じ工場内にあるのは、大きなメリットなのでしょうか。
二宮:メリットは大きいと思います。
製品を設計し、それを自分たちで試験をするわけですから、もし品質保証上問題があればすぐに設計と協議ができ、迅速に対応がとれます。
自前ですから試験もいつでも何度でも行えます。同様に製造工程で問題が発生したとしても、すぐに検証できます。
こういったことは質の高いモノ作りをする上で大きなアドバンテージになっていると思います。

■ところで、このデノンブログで開発者インタビューをやっていて、よく開発者の方から「QAからダメが出た」という話を時々うかがいます。
製品を作るときに「ダメ」を出すのは、社内的にも結構大変な仕事ではないかと思うのですが。
橋本:たしかに製品の開発者と製品の認定をする人間では製品に対する立場が違います。
でも、両者共にが目指している目標は同じなんですね。
「デノンとして信頼性が高い、いい製品を作る」ということ。実際に設計のエンジニアは細部まで入り込んで設計します。
その製品を我々はもっと広い視点で、あるいは一般の方に近い視点で検証していきます。
ですから設計者が見つけられなかった問題点も見出すことができ、設計がそれを対策する、それによって結果としてよりよいデノンの製品ができあがります。
二宮:それにQAからの指摘に関しても、決して杓子定規に対応しなくてはならない、というわけではありません。
QA検査で問題は発生したけれど、実際にユーザーの声を聞き、現実的に本当に問題があるのかを精査してみて、場合によっては協議の結果「対策の必要はない」という結果になることもあります。

■ちなみに設計段階が見逃していた大きな問題をQAがスーパーセーブしたということはありますか。
あのまま市場に出ていたらクレームの嵐だったかもしれない、というような……。
二宮:(笑)大きな声では言えませんが。
橋本:ないとはいえませんね(笑)。
■最後にQAの仕事をやっていて良かったと思うのはどんな時ですか。
二宮:やっぱりユーザーの声を聴いた時ですね。
自分が担当した製品がネットの評価などでお褒めの言葉をいただいたのを見たりすると、ああ良かったな、と思います。
■二宮さん、橋本さん、2週にわたりありがとうございました。
(Denon Official Blog 編集部 I)